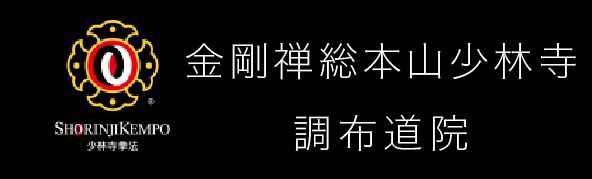おはようございます。管理人です。
調布道院ではここ数ヶ月、月に1回門法修学を行っています。
担当者を決めて発表して、次の担当者を決めて、翌月発表して・・・
という流れです。
昨日は私が担当でした。
何をやろうか・・色々考えたのですが、大拳士試験の課題
「少林寺拳法教範第一編の主旨およびその構成について論ぜよ」
をやることにしました。
教範、僧階教本、『少林寺拳法教範』第一編 註解、を駆使して
ここがこうで・・これがこうだから・・それでこうか!
といった感じで最終的にA4一枚の資料にフローチャートのような形で纏めました。(アップしていいかわからないので載せられませんが。。)
補足資料として「あ・うん 2011 文月・葉月」の”金剛禅の求める「人」とは”を引用させて頂きました。
教範には”金剛禅門信徒の修行法”として外修と内修を説明した図があります。
この図に書かれている托鉢行や持戒行といった言葉。これらがそれぞれ具体的に何を指しているか当時よくわかっていませんでした。
初めてこのあうんを読んだとき「こういうことか!」と理解することが出来、いまも大事にとってあります。※言葉が1つ1つ説明されておりわかりやすいです。
こうして学科をやっているといつも思うことがあります。
それは「この内容はこの前読んだあの本と似ているな・・」と。
学科や教えといった表現をすると「少林寺拳法独特なもの、異質なもの」といった捉えられ方をすることが多いなと感じるのですが、その内容は人生や社会の本質について言及しているのだと思います。
ベストセラーになっているようなビジネス書などはやはり本質を突いています。
本質と本質なので似ていると感じるのでしょうね。
つらつらと書いてしまいましたが、やっぱり学科を通して色々考えるのは楽しいですね。